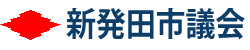
令和7年 9月定例会
令和7年9月12日 (一般質問)
広岡けんじろう
録画を再生
1 身寄りのない方が亡くなられた際の遺留金・遺骨の取扱いについて
2 エンディングサポート事業(終活支援)について
1 身寄りのない方が亡くなられた際の遺留金・遺骨の取扱いについて
家族形態の変化や地域のつながりの希薄化などにより、高齢者の単身世帯は年々増加しています。その結果、身寄りのない方が亡くなられた際には、遺骨を誰が引き取り、どのように保管するのか、また亡くなられた方が所持していた金銭や預貯金等(遺留金)をどのように扱うのかといった問題が生じます。これらはすでに全国各地で深刻な課題となっております。
行旅病人及行旅死亡人取扱法(こうりょびょうにんおよびこうりょしぼうにんとりあつかいほう)(行旅法)や墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)に基づき、市が葬祭を実施するケースもありますが、遺骨の引取者がいない、あるいは引取りを拒否される事例も少なくありません。その結果、市がやむを得ず遺骨を保管する状況が生じていると考えられます。
令和5年3月に総務省行政評価局が公表した「遺留金等に関する実態調査結果報告書」によると、引取者のない死亡人の発生状況に関する基礎調査の対象とした1,741市区町村のうち、回答を得られたのは、行旅法について1,078市区町村、墓埋法について1,068市区町村、生活保護法について691市区町村でした。
平成30年4月1日から令和3年10月末日まで(以下「基礎調査対象期間」という。)の間における引取者のない死亡人の発生件数は、3法合計で10万5,773件。
当市において過去5年間のデータによれば、行旅法第7条適用によって火葬を行った件数(身元不明の遺体)は0件。
墓埋法第9条適用により火葬を行った件数(身元はわかるが火葬を行う者がいない)はR4年は1件、R5年は2件、R6年は5件。
生活保護法18条第2項により火葬をおこなった件数は、R3年1件、R5年3件、R6年2件となっております。
さらに、令和3年10月末時点において引取者のいない無縁遺骨を保管している市区町村は822自治体にのぼり、保管柱数は5万9,848柱に達しており、地域を問わず多くの自治体が無縁遺骨の対応に苦慮している実態が明らかとなっています。
身寄りのない方が亡くなった場合、その葬儀や火葬の費用には、まず故人が残したお金(遺留金)を充てることになっています。その後、相続人が見つかれば費用を請求し、さらに不足する場合は自治体が負担する仕組みです。
しかし実際には、この「遺留金の扱い方」について明確なルールがなく、自治体ごとに対応が分かれているのが現状です。国でも遺留金等の取扱いに関する手引きを作成し周知する取り組みが進められていますが、相続人を調べる方法や遺留金をどこまで使えるかといった点は、まだ実務に合った形で整理はされていません。
高齢者の単独世帯が増加する社会状況を背景として、遺骨の取扱い、遺留金の問題は今後さらに深刻化することが懸念されます。
これらの事例を踏まえると、当市としても遺骨・遺留金の保管や費用負担のあり方について、条例や要綱による制度整備を検討すべき時期に来ていると考えます。以上を踏まえ質問させていただきます。
(1) 行旅法及び墓埋法に法律に基づき、市が葬祭を行った場合の遺骨の取扱いについては、法令上の規定はなく、遺骨の引取者がいない場合、または引取りを拒否された場合には、市がやむを得ず遺骨を保管しているものと考えられます。
また、生活保護法に基づき葬祭扶助を支給した場合においても、第三者が葬祭を実施した場合には、必ずしも葬祭実施者が遺骨を引き取るとは限りません。この場合も、遺骨の引取者がいないときには、保護の実施機関がやむを得ず遺骨を保管しているものと考えられます。当市において引取者のない死亡者の遺骨を保管しているのか。また保管している場合には、現在保管している柱数について教えてください。
(2) 引取り者がいない遺骨は、現在どの様な場所に安置されておりますでしょうか。保管場所の余裕はあるのでしょうか。
(3) 兵庫県神戸市では平成27年に全国で初めて遺留金の取扱いに関する条例を制定し、葬祭費用への充当や相続人調査への活用について明確なルールを定めました。
千葉県香取市や岐阜県美濃加茂市、茨城県龍ケ崎市などでは「遺留金等取扱要綱」を設け、遺留金の管理や供託、家庭裁判所への申立て、場合によっては寺院への納骨などの手続きを明文化しています。
こうした他市の取組みを踏まえ、当市においても遺留金の取扱いに関する条例または要綱を制定すべき段階に来ていると考えますが、市長のお考えをお聞かせください。
2 エンディングサポート事業(終活支援)について
終活支援を開始する自治体が増加しており、その一つの取組で2015年から横須賀市で開始したエンディングサポート事業があります。
エンディングサポート事業とは、身寄りのない方や単身高齢者などが、生前に協力葬祭事業者と葬儀・納骨等に関する契約を結ぶことを支援するものです。この様な事業を開始する自治体が年々増加しております。
まず、市が相談を受け付け、生活状況を聞き取ったうえで本事業の対象となるかを確認し、その後、事業に協力する葬祭事業者の情報を提供、相談者と葬祭事業者の間で希望する葬儀や納骨の内容について合意が得られた場合には、市職員の立会いのもと、生前契約(死後事務委任契約)を締結します。必要な費用については、葬祭事業者に預託金を収めていただくことになります。市は登録者に対し、定期的に生活状況の確認を行うほか、関係者への情報提供も行い、本人が亡くなられた際には、契約内容に基づき葬儀・納骨が行われ、市はその履行状況を確認する流れになります。
今回の一項目の身寄りのない方が亡くなられた遺留金・遺骨の取扱い場所等についての質問も踏まえ、この様な終活支援制度は今後必要と思われますが、市長のお考えをお聞かせください。