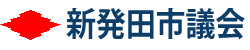
令和7年 9月定例会
令和7年9月12日 (一般質問)
小坂博司
録画を再生
1 本市の米政策についてその2
2 新発田市の平和教育について
1 本市の米政策についてその2
今年も、見渡す限り黄金色に包まれた実りの秋を迎え、コンバインの振動や乾燥機から漂う熱気を待つ「稔り豊かな田園都市しばた」を迎えつつある。
6月定例会、一般質問を含め引き続き本市の米政策について伺う。
8月5日、政府は、コメ価格が高騰した要因の検証結果について、一般家庭の消費量やインバウンド需要の観点が欠けていたことなどから、コメの生産量が不足していたことを認めた。その上でコメの増産にかじを切る方針を表明した。
そして農場経営の大規模化・法人化やスマート化と共に農地を次の世代に繋いでいくと「増産に前向きな生産者」に支援するとしている。
1971年以来50年以上続く「減反政策」からの大転換であるが、長く続いた生産調整は、コメ生産者にとって生活が成り立たないなど苦境に置かれ、後継者不足による高齢化が顕著となり、やがては耕作放棄地の増加等で農地の荒廃化が問題となっている。
8月19日、JA全農にいがたは2025年の「仮渡し金」の額を発表し、昨年度比7から8割高い大幅増の金額を示した。コメ生産者は「この金額ならば農業資材の値上がりを含めても利益が十分出る」とする一方で、「消費者に食べてもらってはじめて農家は成り立つ。買ってもらえなくなる高値になったら意味がない」とコメ離れを危惧する声もある。
当市は田耕地面積9,500haを有し、新潟市、長岡市、上越市に次ぐ4番目の稲作地帯でありコメ政策の転換は市政全般にわたる転換期であると考える。
このことを踏まえ、コメ生産者の意欲が全市民の元気につながって欲しいと願い3点について伺う。
(1) 米の増産には作付け面積の拡大に向け取組む必要がある。次年度には間に合わないとしても、2年後には拡大に向けた数値を示しながら、支援策等を計画的に進める必要があると思うが如何か。
(2) 新たな「農場経営の大規模化・法人化」に向けた主な支援策を伺う。また、既存の法人を含め、老朽化した農機・農具及びスマート化の支援策についても伺う。
(3) 2012年度に着工した「国営加治川用水農業利水事業」は、本年10月、ついに完工式を迎える。飯豊山系からの自然豊かで豊富な恵みを充分受ける稲作地域である。ここから収穫されるコシヒカリ等を「加治川米」としてブランド化し地域の活性化に挑戦する意向について伺う。
2 新発田市の平和教育について
今年は昭和元年から100年、そして大戦終結から80年の歴史的節目の年に当たり、戦争と平和について学びなおし、未来への夢と希望を語り合える年としたいものである。
7月25日、日本財団は「18歳意識調査」で、太平洋戦争について「しっかり学んだ」と答えた割合は27.4%にとどまり、戦争体験者から直接話を聞いたことがある人は3割強だったと公表した。
広島平和公園で、海外からの観光客を相手にボランティアガイドをする佐々木駿さん(小学校6年生)は、広島平和記念式典での子ども代表「平和への誓い」において、「私たちが被爆者の方々の思いを語り継ぎ、一人一人の声を紡ぎながら平和を創り上げていきます」と誓った。
また、教育基本法第1条(教育の目的)では、「人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身と共に健康な国民の育成を期す」としている。
一方、当市においては、平成9年6月「わたしたち新発田市民は日本国憲法の平和を希求する理念を堅持し、核兵器のすみやかな廃絶で平和な国際社会を築く」と「核兵器廃絶平和都市」を宣言している。そして毎年「しばた平和のつどい」や「原爆パネル展」などを開催している。
このことを踏まえ、恒久平和への思いを更に繋いで欲しいと願い2点について伺う。
(1) 戦後80年平和祈念事業として「平和のつどい」や「灯りと音楽のゆうべ」等を開催したが、その成果と課題、そして今後の取組みについて伺う。
(2) 原爆パネル展では、7階市民ギャラリーにおいて市内の小学生が作成した「平和メッセージ」の展示が行われた。市内小学生が人権や平和についてよく学ばれていると感動した。小中学校の平和教育の現状と課題、そして今後の取組について伺う。