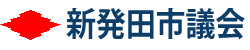
令和7年 9月定例会
令和7年9月12日 (一般質問)
阿部聡
録画を再生
1 人口増に向けた支援策を
1 人口増に向けた支援策を
新発田市のホームページで公表された国勢調査の結果によると、平成22(2010)年の新発田市の人口は101,202(男性48,606 女性52,596)人、平成27年(2015)年の新発田市の人口は98,611(男性47,412 女性51,199)人で平成22年に比べて全体の率で約2.6%の減、15歳から64歳までの生産年齢人口は約7.1%の減であります。
令和2(2020)年の新発田市の人口は94,927(男性45,963 女性48,964)人で、平成27年に比べて全体の率で約3.7%の減、15歳から64歳までの生産年齢人口は約8.3%の減であります。
平成22年と令和2年の10年間で比較すると人口で約6.3%の減、生産年齢人口は約14.9%の減であります。全人口の減に対し、生産年齢人口の減の割合が非常に大きくなってきたのが特徴です。
上記の数字は「出生数の減少」、つまり「自然減」によることは明らかですが、新発田市で高収入を得られる「働く場所が少ない」ことで、より良い働き口を求めて新発田を出ていく人、つまり「社会減」も多いことを示しています。老人介護施設や建設現場などでの働き手不足は極めて深刻ですし、農業現場では人手をかけないスマート農業化が急がれています。老人介護施設は外国人労働者がいなければ成り立ちませんし、建設現場は実現すべき「働き方改革」の推進によって、費用と納期に影響が出ています。農業現場はスマート器機導入が経費増につながっています。
(1) 一時、県内他市町村に先駆けて実施された新発田市の子育て支援策などが功を奏し、また新々バイパスの存在などで新潟市までの通勤時間が短いことなども相まって、「社会減」にストップがかかりました。しかし、他市町村も子育て支援策を充実させ、働き口としての新潟市の優位性が低下(進学先としての優位性も低下)し、当市の市街化開発も一段落して「社会減」は再び増加に転じております。
折しも来年度の予算作成時期であります。人口増を目指して「出生率向上に向けた支援策を強化」してはいかがでしょうか。「自然増」を図る政策の実施です。たとえば、新発田市で高収入が得られる「働く場所を増やすための施策を強化」してはいかかでしょうか。
(2) 人口減少は全国的な問題で、もちろん縮小均衡策も必要ですが、同時に出生率向上・高収入が得られる働き場所増加に対する支援は必須の政策課題であると考えます。出生率増加に向けた市長のお考えを伺います。