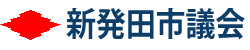
令和7年 9月定例会
令和7年9月11日 (一般質問)
若月学
録画を再生
1 うすがもり保育園の廃園について
2 急増するクマ被害から住民の命を守る
1 うすがもり保育園の廃園について
山間地及び中山間地を今後どのように活性化していくのか、「子育てするなら新発田」などと本当に胸を張っていえるのか。バランスのとれた産業構造を考えるならば林業や農業を含めた第一次産業も市としてきっちりとした「羅針盤」を定めることも必要と考えていく必要があるのではないでしょうか。そのとどのつまりが廃校問題や統合問題に象徴されるのではないでしょうか。
さて、新発田市立うすがもり保育園は、平成14 年に開設された当市では比較的新しい保育園として米倉小学校区を中心にへきち保育所を統合するような形でが設けられ運営されていたました。米倉地区の市立の保育園として健やかな園児の育成に寄与してきました。
しかしながら、中山間地では近年の急激な過疎化や少子化により子ども出生数が著しく減少してきました。このことにより、保育園存続を危ぶまれていました。うすがもり保育園は、地域の期待を担って保育方針として十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定を図る。健康で明るく生活力のある子ども。やさしさ、思いやりがあり、”ひと”を大切にする子ども。自然を愛し、豊かな感性を持った子ども。思ったこと、感じたことを伝えあえる子ども保育の特色(保育内容で特に力を入れていること・主な行事など) 地域に愛されて小学校の校歌にも歌い込まれている『うすが森山』に象徴されるように、四季おりおりの豊かな自然の中で、子どもたちが生き生きと楽しい経験がたくさんできるように、また、花・野菜栽培などを通して、心豊かに育つよう保育し、「子育て支援室」があり、未就園の親子の交流、子育て相談の場として利用していただいていました。
また、子どもデイサービスや地域子育て支援センター:未就園児とその保護者を対象に地域の保育に関する情報発信や家庭的な支援を実施し、誰でも利用できる親子遊びや交流の場でとして活用されてきました。
しかしながら、楽しく学び合った保育園も残念ながら現在6 名となり残念なことに閉園する運びになりました。
このことは、小学校統合と同じくまた一つ地域の灯火が消え失せていくことと言っても過言ではありません。
そこで数点質問させていただきます。
(1) 閉園に至るまでにどのような経緯があったものか。
(2) 開園中に、新たな園舎の形を模索し、地域との融合型保育園として、老人福祉施設と保育園機能を融合したモデルケース的運営を検討したものか。
(3) 比較的新しい園舎であるが、白旗降参「廃園」でなく民間譲渡などを検討したものか。
(4) このままではこれをきっかけに中山間地の活力は衰退の一途であり、この衰退に歯止めをかけるために、今後の中山間地の活性化や人口増加に対してどのような有効な施策を講じるつもりか。
2 急増するクマ被害から住民の命を守る
令和7年9月1日より鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律が改正され、クマが市街地等で出没した場合であっても、市長の許可により猟銃による捕獲が可能となった。
本年(2025年)、全国的にクマによる人身被害が急増し、過去最悪レベルに達していると報じられています。4月から7月末までの間に全国で55人が被害に遭い、北海道・岩手・長野では死亡事例も発生しています。
さらに当市においても、住宅地や農地に隣接する生活圏でクマが出没する事例が確認されており、8月には秋田県北秋田市でランニング中の男性が襲われる被害も起きました。このように「山奥に限らず、市街地や公園など人々の生活圏で被害が発生している」ことは、従来の想定を超えた深刻な状況であると考えます。環境省の見解によれば、今年は暖冬による冬眠期間の短縮や山林でのエサ不足(ブナやミズナラの不作)が大きな要因とされています。
また高齢化・過疎化による農地管理の不十分さや、家庭・事業所における生ゴミ管理の不徹底が「クマを呼び寄せる環境」をつくっているとも指摘されています。
人命を守るためには「遭遇を避ける環境づくり」が不可欠です。特に以下の点が重要と考えます。生ゴミや農作物残渣の適正管理、耕作放棄地や放置果樹への対策、キャンプ・登山・観光客への啓発、学校での防災教育の強化などです。クマによる人身被害が発生した場合、警察・猟友会・自治体が連携して対応することになります。
一方で、過度な抗議や苦情がハンターや自治体職員の活動を萎縮させ、結果として住民の安全確保が遅れる事態も報じられています。
そこで、先般、当市が新潟県内初の「ツキノワグマ出没対応訓練」実施しましたが、反省を踏まえて今後の取り組みを含め現状、要因と分析、予防、緊急時対応等について質問させていただきます。
(1) 現状について
① 令和7年度、把握しているクマ出没・被害の状況は。
② 近隣自治体や県との情報共有はどのように行われているか。
(2) 被害増加の要因と分析について
① 当市周辺における出没要因の分析はどのように行われているか。
② 今後も被害が増える可能性が高い中、どのような警戒レベルで臨むべきと考えているか。
(3) 住民の安全確保と予防対策について
① 住民・学校・観光客に対してどのような注意喚起・教育活動を行っているか。
② 農地や果樹園の管理支援、電気柵設置補助など「共助」を促す取組みはあるか。
(4) 緊急時対応と駆除の在り方について
① 緊急時に迅速かつ安全に対応するための実施訓練を行った結果、反省点はなかったか。
② 駆除を含む対策に関する市の基本的な考え方、そして住民への説明・合意形成のあり方についてどのように検討しているか。