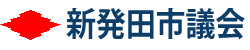
令和7年 9月定例会
令和7年9月11日 (一般質問)
渡邊喜夫
録画を再生
1 リチウムイオン電池の適正な処理について
2 農地の担い手を協議した地域計画の今後の課題について
1 リチウムイオン電池の適正な処理について
近年、スマートフォンやモバイルバッテリー、電動アシスト自転車、電動工具、更には加熱式たばこ機器等、幅広い製品にリチウムイオン電池が使用されています。リチウムイオン電池を使った製品が他のごみと混ぜて捨てられ、処理の過程で発火する事故が増えています。充電して繰り返し使えるリチウムイオン電池は、劣化すると内部に可燃性のガスがたまり、この状態で強い衝撃が加えられた場合に発火の危険性が高まります。2023年度には、ごみ収集車やごみ処理施設における発火、発煙、火災が全国で2万1751件発生しています。事故が年々増えている背景には、電池の取り外しが難しい製品が急速に普及しており、利用者が適正な廃棄方法の情報に触れる機会が少ないなどがあります。家電量販店や新発田市では公共施設に回収ボックスを置いていますが、重要なのは利用者への周知です。また他の自治体ではリチウムイオン電池の危険性や処理に関する出前授業を小学校で開催し、児童の知識向上とともに家庭での分別促進つなげるなど教育面からアプローチしている事例もあります。正しく廃棄し事故を未然に防ぐため、3点伺います。
(1) 新発田市でリチウムイオン電池が原因とみられる火災事故は過去、何件発生しているか
(2) 市として、リチウムイオン電池の適正回収(家電量販店、公共施設の回収ボックス)を市民にどのように周知しているか
(3) リチウムイオン電池の危険性を市民に周知し誤排出を防ぎ、事故防止と資源循環への啓発を学校や自治会等を通じ、更に行うべきではないか
2 農地の担い手を協議した地域計画の今後の課題について
農業を取り巻く環境は、農業者の高齢化や担い手不足、耕作放棄地の増加など深刻な課題に直面しています。国に於いては2012年度にスタートした人・農地プラン(地域農業マスタープラン)の作成をし、紆余曲折を経て2022年から地域の話し合いを通じた農地の担い手の明確化、将来にわたる農地利用の姿を示す「地域計画」の策定を行いました。市担当者、農業委員、農地最適化推進委員等が地域ごとに地元農業関係者等と協議を重ねて、現状の地域農業と今後の農地の担い手確保とともに、農地の集積・集約化への地域計画づくりが進められました。そして10年後の目標地図とともに結果を公表しました。地域計画の推進は新発田市の農業の将来像を描く重要なステップです。今後どのように課題を解決し、持続可能な農業の実現に取組んでいくのか5点伺います。
(1) 新発田市では地域計画の策定が終了し、各地域の担い手や農地の分散など、現状をどのように認識しているか
(2) 高齢化が進む中で、将来の農地を担う若手農業者や新規就農者の確保は不可欠である。地域計画を契機にどのような担い手支援策を強化していくのか
(3) 農地中間管理機構をはじめとする制度を活用し、地域計画で示された担い手へ円滑に農地を集積していくため、市はどのように関与、支援していくのか
(4) 法人経営体や集落営農組織等、地域の担い手の経営基盤強化に向けた支援策は
(5) 全国的な課題である中山間地域の圃場整備等ができない条件不利地の担い手の状況は、10年後どころか現在も担い手がいない地域がある。展望が描けない困難な地域の今後の戦略について