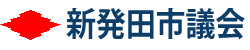
令和7年 2月定例会
令和7年3月3日 (一般質問)
渡邊喜夫
録画を再生
1 帯状疱疹ワクチンの定期接種化について
2 主食用米の高騰と需給調整について
1 帯状疱疹ワクチンの定期接種化について
帯状疱疹は水ぼうそう初感染後、生涯にわたって神経に潜伏感染しているウイルスが加齢、疲労、免疫力低下によって発症します。50歳代以降で罹患率が高く、70歳代でピークとなり帯状疱疹後神経痛も50歳〜60歳代と比較して70歳代以降で増加すると厚生科学審議会で示されております。
新発田市の帯状疱疹ワクチンの任意予防接種費用の一部助成については令和6年度から開始されました。対象者は50歳以上からであり助成額は生ワクチンの1回接種が2,300円、不活化ワクチンは2回接種で1回あたり5,300円の一部公費助成が受けられるようになりました。市民からは「助成してもらえてとても助かった」との声を頂いています。全国的に自治体の任意接種助成は広まっており、令和6年11月現在に於いて新潟県内では15自治体が実施し、全国では731自治体にも上っています。助成内容を見ると生ワクチン、不活化ワクチンともに半額程度を助成している自治体が最も多く、不活化ワクチンは高額ですが、効果の高さから接種希望も多いようです。
昨年6月に厚生労働省の国立感染症研究所の分析結果から、生ワクチンと不活化ワクチンのいずれについても有効性や安全性が確認され、費用対効果は良好となったことを踏まえ、帯状疱疹をB類の定期接種に含めることになり、令和7年4月から原則65歳を対象に定期接種が開始されます。高齢者肺炎球菌ワクチン同様に、5年間の経過措置として70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上に接種する機会を設けます。そこで定期接種化に向けた体制等について市長に6点伺います。
(1) 今年度、50歳以上を接種対象者とした帯状疱疹ワクチンの任意予防接種費用の助成を受けて接種した人数及び接種率、執行予定の助成額の見込みについて見解を伺います。
(2) インフルエンザワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチンそして新型コロナワクチンと同様にB類定期接種となる場合、地方交付税で措置されるのは3割程度との認識で良いか伺います。
(3) 帯状疱疹の予防と重症化を防ぐ効果があるとして、50歳以上の全ての年齢が任意接種の対象者であったが、令和7年4月からB類の定期接種への移行によって対象年齢が65歳となる。免疫不全のある方は60歳〜64歳も対象者となります。これまでの50歳以上すべての年齢を対象にしていた接種助成を見直すことになれば市の予防接種が後退すると考えるが見解を伺います。
(4) 定期接種移行時における接種対象年齢を令和6年度同様に50歳から独自助成をした場合、市の事業予算の推計はどれくらいか伺います。
(5) 令和6年10月1日現在の新発田市の50歳以上の人口49,209人ですが、ワクチン未接種の場合における帯状疱疹の罹患者数及び帯状疱疹神経痛患者数を全国的な統計の数値から推計した場合、何人が罹患し、年間の医療費はどれくらいになるか伺います。
(6) 令和7年4月1日以降も任意帯状疱疹予防接種助成を継続する自治体がありますが、当市の帯状疱疹ワクチン予防接種に関する見解を伺います。
2 主食用米の高騰と需給調整について
平成30年から行政による生産数量目標の配分が廃止され、減反政
策が終了し、生産者はそれぞれの地域の特性等を考えながら、自らの経営判断により、需要に応じた米の生産と販売を行うことになりました。生産者個人がより自由に主体的な判断により米の生産量を決められるようになりましたが、米の消費量(需要)が人口減少や食の多様化によって年間約10万トンが減少している中、過剰生産による米価の下落を防ぐため需要に見合った生産が重要です。
昨年、農政の憲法とも呼ばれる「食料・農業・農村基本法」が四半世紀ぶりに改正されました。今年は、改正法を踏まえた食料・農業・農村基本計画の策定が予定される他、令和9年を目途に水田政策の見直しが予定され農業政策は大きな転換点を迎えています。
食料自給率・食料自給力の向上等を図る観点から、水田をフル活用し、需要のある米粉用米、加工用米、輸出用米等の戦略作物や高収益作物の園芸品目や大豆、麦等への転換を積極的に進めることも重要です。
昨年は、令和5年産米の精米歩留まりが低下したこと等により、全国の主食用米の民間在庫量が、過去最少を記録したことに加え、8月の南海トラフ地震臨時情報による米の買い込みや、インバウンドによる米の需要増等の背景によって全国的な米不足が生じて「令和の米騒動」が起こりました。主食用米の価格は現在でも大きく上昇しています。そのため米価の高騰による消費者の米離れへの懸念と、投機的な米の買い占めへの抑止力効果を期待して政府備蓄米を機動的に活用する方針が決まり、3月から適切な運用が始まる予定とのことです。
しかし需給の帳尻合わせは実質、今年の主食用米の作付け増減でバランスをとることになります。主食用米が高騰している中、生産者の主食用米増産への意識が高まっています。主食用米の過剰生産を抑え、需給調整へ誘導しながら生産者の所得の向上に向けた水田政策が重要になってきます。そこで3点について伺います。
(1) 主食用米の需給調整の現状と非主食用米の需要に応じた生産誘導策について
(2) 昨年、オーガニックビレッジ宣言を行い有機米生産などの推進や更なる輸出拡大への取組を行ってきましたが、令和6年産の有機米生産の状況と、現下の主食用米の高騰による影響について伺います。
(3) 主食用米の高騰による政府の備蓄米放出の決断について市長の見解を伺います。