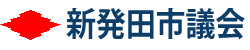
令和7年 2月定例会
令和7年2月28日 (一般質問)
惣山かすみ
録画を再生
1 子供たちの一人一台端末の学力
2 オーガニック食材を給食に導入しては
1 子供たちの一人一台端末の学力
GIGAスクール構想において、小・中学校「一人一台端末」の導入が終わり、保護者や教師から様々な意見が上がってきています。
保護者からの意見としては、時代の変化に追いつくのは大切だけどと前置きしながらも、書くことが減ったため子どもたちが字を覚えにくくなった、子どもたちが「考えること」を面倒くさがるようになった気がする、低学年は重くて登下校がかわいそう、生活リズムへの影響、デジタルデバイスの家庭での指導が難しい、いっその事学校で決まりを作ってほしい、視力や心理面に対する影響が不安などと声がありました。
教師の意見としては、教師から宿題管理など業務が楽になった、授業などで動画を取り入れることで理解度が増した、グループワークで発表の機会が増えて良い、自宅に持ち帰って仕事ができてしまうのでプライベートと分けにくくなった、などです。
調べてみると、世界では先んじてICT教育を取り入れている国から様々な声明や研究結果が出ています。
IT先進国のスウェーデンでは、2010年から「一人一台」端末を進め、近年は紙の教科書を廃止し、デジタル教科書に完全移行していましたが、2023年8月の新学期からは、印刷された書籍に新たな重点を置き、ICTを活用する時間を減らし政策転換しています。また、スウェーデン最大の研究教育機関であるカロリンスカ研究所は「デジタルツールが生徒の学習を向上させるのではなく、むしろ妨げる。デジタルメディアが生徒に利益をもたらすのではなく、害を及ぼすことに疑いの余地はない。画面上で読んだ内容の読解力と、記憶力は30%以上低下し、インターネットで資料を検索する生徒は従来の教科書よりも明らかに劣る」と主張しています。
他にも学力世界一のフィンランドでは、特に男児や若者のゲーム依存により急激な学力の低下が確認され、家庭での読書強化施策を取り入れています。ニュージーランドやドイツでも、同様です。
国内を見てみると、鹿児島県与論町では、小学校はデジタル端末の持ち帰りをせずに紙の宿題を出しています。
令和5年の子ども家庭庁の調査によると、インターネットを利用する平均利用時間は、前年度と比べ増加傾向にあり、 高校生は、約6時間14分。中学生は、約4時間42分。10歳以上の小学生は、約3時間46分で 目的ごとの平均利用時間は趣味・娯楽が最も多く、約2時間57分でした。
もちろん趣味や、娯楽に使ってはいけないと言うことではありませんし、従来の学習方法ではなく、子供たちが課題を見つけ、自ら調べ、まとめて発表するなどの主体的な学びや、探求型の学びにおいては、デジタルデバイスは成果を上げている事例もあります。
ですが、子供たちのデジタル活用には学力だけではなく、健康、特に目やメンタルヘルス、体内時計への影響、ネット依存やゲーム依存のリスクなどもあります。
これらをもって、以下質問いたします。
(1) 平日において子どもたちは、小中学校の授業や宿題にデジタル端末を毎日使用し、宿題等自宅学習でも半数の児童が3〜4日使用しているとのことですが、体力や健康面に与える影響を考慮し、紙の宿題を出すなど対応の変更は検討されているか。
(2) タブレット端末の導入により、教師の負担軽減に繋がる半面、自宅でも仕事ができてしまうなどの声もあると聞いています。デジタルデバイスによる教師へのメンタルヘルスの影響が憂慮されるが、タブレット端末を持ち帰らない等の対応はされているか。
2 オーガニック食材を給食に導入しては
市の掲げる施策であるオーガニックSHIBATAにおいて、市ではオーガニック米の輸出に取り組み、3年が経ちました。昨年の学校給食にオーガニック農産物を取り入れられないかの一般質問に、市からはそもそもいただいている輸出の発注量に対して追いついていない現状であることと高額であるため、まずは年1回学校給食に導入したいとの答弁がありました。
オーガニック農法や減農薬、自然農法は、脱炭素社会の達成、土壌汚染や水汚染を防いで生物多様性を保全する持続可能な社会の達成、郷土愛を育くむことや環境教育、移住促進、そして健康になることで出生数が増え、なにより健康長寿に貢献します。これは、市の「住みよいまち日本一 健康田園文化都市・しばた」においての将来都市像実現のための4つ視点、健康長寿、少子化対策、産業振興、教育の充実を網羅しています。
また昨年、市民活動としてオーガニックフェスタや有機に関する講演会が開かれ、今年3月には、県内のオーガニックビレッジ宣言市町村の取り組み報告会も新発田市共催のもと、開催が決まっています。中でも、札の辻広場で行われたオーガニックフェスタは5,000人程の集客があり、開催側も驚いたほどです。
ガソリンの高騰による、海外産の農薬や化学肥料などの物価高騰により、農産物の価格高騰もみられる中、オーガニックだから高いということもなくなってきています。
以上を踏まえて、以下質問いたします。
(1) オーガニックや減農薬に取り組んでいる農家を把握していますか。
(2) オーガニック米は輸出のみになっていますが、減農薬米や米以外の野菜などの市内オーガニック農産物、または減農薬野菜を学校給食用に市で買い取る、給食食材の標準的な価格との差額分を補助するなどの応援はできないでしょうか。