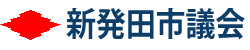
令和7年 2月定例会
令和7年2月28日 (一般質問)
若月学
録画を再生
1 スフィア基準に基づく避難所運営指針
2 個人情報保護と募金活動
1 スフィア基準に基づく避難所運営指針
2024年1月1日午後4時頃発生した令和6年能登半島地震では、M7.6の地震が発生し、この能登半島地震が原因で2024年11月現在では災害関連死は約200名となり、直接死も含めた死者は約430名となりました。
その後の、4月3日午前8時頃、台湾の東部沖沿岸を震源としたマグニチュード7.4の地震が発生。 花蓮(かれん)市で震度6強を記録したほか、広い範囲で揺れが発生し、日本の沖縄、フィリピン沖でも津波警報が発出されるなど、大きな影響を及ぼし、この地震により18名の犠牲者と1,163名の負傷者、2名の行方不明者とされています。
この2つの地震は双方ともマグニチュード7.6と7.4と大規模なレベルの地震であり、能登半島地震と花蓮地震は確かに土地の地形や発生した時期など多くの違いがありましたが、どちらも大規模な建物の倒壊や高層ビルが傾くなど、建物の損壊が沢山ありました。
しかし、台湾の避難所運営や人々へのヘルスケアの違いをまざまざと見せつけられました。日本の避難所の基本的な避難所運営プランについてどうなっているのか疑問を持たざる得ません。台湾での避難所運営で一番印象的であったのは体育館にプライベートを確保するために仮設のテントを個別に張られている光景でした。
なぜこのように国によっての対応が違うのかを知ることが出来たのは当市出身の国際医療福祉大学災害保健医療研究センター 副センター長 石井 美恵子(いしい みえこ)教授からご連絡を頂いただいことがきっかけでした。
ご自身が避難所解説者となり、「海外から学ぶ避難所の運営」と題したテレビ番組で、イタリアと台湾の避難所事情のテーマで各国の違いなどについて解説しておられました。
第一に避難所はヘルス(健康維持)の場であり、健常者や障がい者、老若男女すべての人達が健康を維持することであること。
このことは、「スフィア基準」で定めてあり、アフリカ・ルワンダの難民キャンプで多くの人が亡くなったことを受けて、国際赤十字などが20年前につくり、後に、災害の避難所にも使われるようになったとのこと。紛争や災害の際の避難所の環境について、“最低限の基準”を定めています。
たとえば、居住空間については、1人あたりのスペースは、最低3.5㎡(約1坪)確保すること。熊本地震の避難所では、避難者1人あたりのスペースが1畳分(1.62㎡)ほどしかない場所もあったとのこと。
また、トイレについては、「20人に1つの割合で設置しさらに男女比は「男性と女性の割合は1対3」であるそうです。
避難所で大事なのは「水分をとり、こまめに動くこと」だそうです。1人あたりのスペースが狭いと長時間同じ姿勢でいることが多くなり、トイレが汚れていたり混んでいると水分をとるのをためらう人が多く「血栓」がおこり関連死の原因になることも多いとのことです。
また、イタリアの避難所運営では、発生から72時間以内に、家族ごとにテントやベッドが支給され、衛生的なトイレも、整備されたということです。
これに対し、日本では「スフィア基準」が浸透せず、劣悪な環境の避難所が設置され続けており、「我慢は当たり前」という意識を変えることが必要です。
「スフィア基準」自体、南海トラフ巨大地震の被害が想定される徳島県では、平成29年、避難所運営マニュアルにスフィア基準を盛り込んだことです。
これらの事を踏まえて当市において少なくても「スフィア基準」を鑑み推進できる事から取組を開始しなければならないと思い質問させていただきます。
(1) スフィア基準は、あくまでも最低基準。その基準を元に地域に合わせたよりよい避難所運営が大事であると考えます。概ね20人に1つのトイレの確保が必要であり、なおかつ、トイレ男女比1対3がクリアできているのか伺う。また今後どのように考えて行くのか。
(2) 市の避難所において、スフィア基準に沿って行動計画を策定する場合、避難所テント数及びダンボールベット等はどれくらいの数が必要となるのか。また、現在の避難所計画で対応出来ているのか。
(3) 血栓防止対策として「1人あたりのスペースは、最低3.5㎡確保すること」としているが当市の行動指針は何㎡になっているのか。
(4) 避難所運営は、ヘルスケア(健康維持)が重要である。治療や診察、医薬品などの「医療分野」や栄養、運動、ストレッチ、マッサージなどの健康管理の「健康分野」や「生活分野」が重要である。具体的な対策としてどのような計画があるものなのか。
2 個人情報保護と募金活動
令和6年4月末、当市において転出者の個人情報を本人の同意なく自治会長らに提供していたことが新聞報道で明らかになった。
当市は希望する自治会に情報提供しており、個人情報の目的外利用を防ぐため自治会長らと誓約書を交わし、自治会長らに広報紙配布といった業務を委託している。市内は広く、自治会も300以上あり、災害時のスピーディーな共助につなげたいという考えも根底にあるとし、コミュニティーの維持を考慮した上での対応だとのことであった。
しかしながら、政府機関の個人情報保護委員会の事務局は、情報提供が妥当かどうかは自治体の対応を個別に見る必要があるとした上で「本人以外に提供した個人情報が本人の利益となるか、検討しているかが問われる」と指摘した、とされています。
このように政府が示した個人情報保護の考え方が本人の利益となるかとのこともあり、個人情報と募金に対する考えからについてお聞きします。
この度は、自治会に寄せられた共同募金や寄付に関しての質問をさせていだきます。
現在、多くの自治会では、地区や地域の自治会が主体的に取り組んでいる団体への寄付金として自治会費やコミュニティ支援金、学校関係後援会費、交通安全支部補助金、自治連合会費、地区鳥獣被害対策協議会等の他に市を支える支援として
①市社会福祉協議会費400円、
②青少年健全育成会議200円、
③日本赤十字社への支援金、500円
その他、任意の募金として
①緑の羽根募金、
②赤い羽根共同募金があります。
自治会では自治会長さんから各班長さんへ依頼されとりまとめをお願いしてこれらの多くの募金を要請するケースが多いと思われます。その際、個別募金の袋には、募金の趣旨や目的のほか募金一件当たりの目標金額が記載されております。
このことは、各募金などによっては住民の人達により支援する団体や組織への支援するべき理解や支援に対する考え方に差異があることも現実です。このような実態があるなかにおいて戸別において実質的に各自治会長が取り仕切り募金袋に住所や金額まで記載させているケースもある。この様な行為についてはどの家の人がいくら募金をしたのか一目瞭然であり、個人の真心のこもった募金を管理する事と等しく、言うなれば隣人の思想や良心を侵害することにもつながりかねないことが懸念される。
また、袋の記載金額と袋の中の金額を突合せざる得ない義務も生じかねない。真面目に役務を遂行するとすごい重圧感があるのも事実である。
このようなことから多くの自治会では、募金袋には一切手を付けずに預かった募金袋をそのまま役所の担当へ渡していることも多い事と思います。その後自治会宛に募金者の人数と金額を記載した預かり書が送付されて来ます。
このような事であれば金額を記載する欄は必要なのかも疑問であります。
また、本来「赤い羽根共同募金」においては主催:社会福祉法人新潟県共同募金会、実施者として社会福祉法人新発田市社会福祉協議会が市の窓口となり募金の取り纏めを行っています。この募金のたぐいは、募金することにより「法人税法第37条3項第2号」及び「所得税法第78条第2項第2号」と「地方税法第37条の2、第314条の7」に該当することから募金者が、確定申告の際に税控除の対象となることから「氏名」「住所」を明記する必要があります。しかし、このような重要な事柄については詳しい説明が無いのが実態であります。このような所得税控除ができることなど非常に重要な事柄について自治会長へは何の説明もありません。
このように、募金にも様々なものがありこれらを自治会や市民の皆さんへきちんとした説明をしているかどうかも含めて質問させて頂きます。
(1) 各種団体の任意の募金について個人情報保護の観点から個 人が金額や氏名を伏せたい場合、違和感無く協力するためにどのような事に配慮しているのか。
(2) 募金を取り纏める人(自治会長または班長など)が取りまとめる際、各戸若しくは個人の個人情報保護をするために戸別の募金袋に目隠しシールなどを貼り付け情報を保護すべきと考えるがいかがか。
(3) 赤い羽根共同募金に類似する共同募金会への募金を確定申告で税控除する場合について、自治会長及び班長など取り纏めの方には、適切に説明などを行っているのか。また、控除証明書を何件位交付しているのか。また、交付はどのようにしているのか。