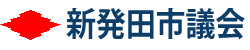
令和6年12月定例会
令和6年12月17日 (一般質問)
高橋茂
録画を再生
1 フィルムコミッションについて
2 道の駅加治川の利用方法について
3 デフリンピックを活用した障がい者教育について
1 フィルムコミッションについて
昨今、映画やドラマ、CMなどの撮影地として選ばれる地域が増えており、これをきっかけに観光客が訪れる「ロケツーリズム」や地域ブランドの向上が注目されています。多くの自治体がフィルムコミッションの精鋭部隊を設置し、撮影の誘致を積極的に行い、経済効果や地域の魅力発信に成功している事例も多く見受けられます。
一方で、新発田市におけるフィルムコミッションの取り組みは、まだまだ十分に力を入れているように感じられません。ご存じのようにこの新発田市には、多くの地域資源や自然環境があります。
そのような資源を活用することで、映像制作の誘致はもちろん、新発田市の魅力を国内外に発信する絶好の機会になると考えております。
(1) 映画「十一人の賊軍」は幕末を背景に制作されています。大倉喜八郎が大活躍する時期は、もう少し先とはいえ、同じ時代の物語になります。蔵春閣で、「十一人の賊軍」を関連付けさせたイベントや広報活動は行ったのでしょうか?また、今後、そのような具体的な計画はあるのでしょうか?
(2) ここまで新発田市を舞台とした映画は、今までになかったと言えます。この映画に敬意を払い、来年も、市民文化会館で再上映する計画はないのでしょうか?
(3) 他市の成功事例を参考にしながら、新発田市独自の取り組みとしてどのようにフィルムコミッションを活用していく計画があるのか、市長のお考えをお聞かせください。
(4) フィルムコミッションを通じて撮影が誘致された場合、地域住民や地元企業との連携で、コラボ商品の開発やロケツーリズムの計画など、地域全体に利益をもたらす仕組みを構築するお考えはありますか?
2 道の駅加治川の利用方法について
道の駅は、観光客や地域住民にとっての休憩・情報発信機能の場であるとともに、地域資源の活用や地元経済の活性化において重要な役割を担っています。その中で、「道の駅加治川」は新発田市の北の玄関口として期待される存在であり、農産物直売所や観光情報の提供、地域イベントの開催など、多くの可能性を秘めていると感じております。
しかしながら、近年では地域間競争の激化や人口減少による利用者の減少など、全国的に道の駅が抱える課題も指摘されています。新発田市においても、「道の駅加治川」をいかに活用し、発展させるかが重要な課題であると考えます。
(1) 現在、「道の駅加治川」における来訪者数や売上の推移、利用者からの要望などの状況、または、地域住民の意見をどのように把握されているのか。また、課題として認識されている点についてお聞かせください。
(2) 道の駅加治川は、今年度予算を割きバーベキュー施設を11月末にオープンしました。しかし、今の時期、バーベキューシーズンは過ぎているように思えます。よって、来春のシーズンに入るまでの間、顧客開拓や周知活動はどのように行うのか、具体的な方針があればお聞かせ願います。
(3) 地元農家や商工業者、住民と連携しながら、道の駅加治川を地域経済の拠点として活性化させる取り組みについて、市長のビジョンをお聞かせください。
3 デフリンピックを活用した障がい者教育について
昨年12月議会、一般質問において「外見では判断できないような聾唖者や知的障がい者に対する共生教育の現状について」教育長より答弁をいただき、その際の再質問で、聾唖や難聴などの聴覚障がい者への理解を深めていただくため「2025年デフリンピック東京大会」をテレビ観戦するなど教育の手段として活用できないか伺いました。
教育長からは、「一番力を入れてきたのは、学力向上はもちろん、いじめ、不登校もありますが、共生社会です。」また「聾唖者という人はどういう人か、障がいがあるってどういうことか。そのために福祉というテーマを設けて、実際にその方にお越しいただいて話をすると子供たちは理解を深めます。」とした上で、「2025デフリンピック東京大会につきましてもこれから研究させていただきたいと思います。」と力強い答弁をいただいたと記憶しています。
9月にパリパラリンピックが開催され、参加した選手のプレイを見て、世界中の人々が感銘を受けたことから、100年目の記念大会になる、2025デフリンピック東京大会を活用することで、聴覚障がい者への理解を更に深められると考え、2点伺います。
(1) 聴覚障がいへの理解を深めるため提案した「2025デフリンピック東京大会活用」について、研究の進捗状況はいかがでしょうか。
(2) 子供達への聴覚障がい者への理解を深めるため、デフリンピック東京大会の活用を含め、学校教育における取組について具体的なお考えはありますでしょうか。