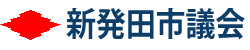
令和6年12月定例会
令和6年12月17日 (一般質問)
三母高志
録画を再生
1 困難な問題を抱える女性への支援について
2 市職員のハラスメント問題について
1 困難な問題を抱える女性への支援について
本年9月末までテレビ放送された朝ドラ「虎に翼」が話題を呼んだ。その放送で描かれた戦前の明治憲法下の家父長制度において日本の結婚した女性の地位は「無能力者」と規定されていた事に、私は衝撃を受けた。
戦後、法律が改正されこの規定は廃止されたが、その後1956年に売春防止法が成立し、婦人保護事業がはじまり婦人相談員などによる取組が行われてきた。
新発田市においても、昭和31年には県内でもっとも早く婦人相談員が配置され、取り組みが行われてきたが平成11年には業務が減った事などを理由に婦人相談員の配置は廃止されている。
社会状況が変化し女性の相談内容や、必要とされる支援の実態がDVや生活困窮、性暴力や孤独・孤立など女性をめぐる課題が複雑化、多様化し、福祉サービスの必要性に重点が移行してきた。
そして残念ながら現在に至るも、男性、女性の違いによる様々な差別が社会的な構造として残されていると認識する。
さて本年4月「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(以下女性支援新法)が施行された。
この法律は、まさに困難な問題を抱える女性が日常生活や社会生活を営むに当たり、女性であることにより様々な困難な問題に直面していることが多いことから、女性の福祉増進を図るため支援し、女性が安心して、かつ自立して暮らせる社会の実現に寄与する事を目的として制定されている。
この法律の意義を深く理解し現在の新発田市における困難な問題を抱える女性への支援と課題解決につなげるため、以下について伺いたい。
(1) 「女性支援新法」では、市町村においても施策実施に関する計画策定について述べているが、今後の新発田市の計画策定の考えについて。
(2) 困難な問題を抱える女性から市の女性相談支援員が受けた相談件数の推移(女性相談支援員設置当初から現在(令和3〜5年度)まで)と相談内容の傾向について。
(3) 新潟県女性福祉相談所が発行している「婦人保護のあゆみ」によれば三条市や柏崎市の相談受理件数と比して、新発田市の相談受理件数が少ないが、その原因について。
(4) 具体的支援に当たり、広く市民への周知が大切であるがどのような周知を行っているか。
(5) 専門性を有する女性相談支援員の現状1名から複数名配備が必要と考えるが新発田市の考えについて。
(6) 女性相談支援員の雇用や待遇の改善が必要と考えるが新発田市の考えについて。
2 市職員のハラスメント問題について
ハラスメントは近年、社会問題としてクローズアップされる重大な課題である。新発田市議会においても過去に多くの論議が重ねられてきている。
本年6月議会における中村こう議員の質問に対し、市長は「国において対策検討段階であり、カスタマーハラスメント防止に特化した条例制定は現時点で考えていない」、「カスタマーハラスメントは重大な人権侵害につながる行為」、「ハラスメント行為は、被害者に長期間に及ぶ精神的、身体的苦痛を与える、その行為はいかなる立場でも決して許されない」等々、答弁されている。しかしこの答弁後も新発田市職員においてハラスメントの問題は継続されていると認識する。
そのハラスメント問題の解決にむけ一歩すすめるため、今回は市職員へのハラスメント問題について特化し、新発田市の現状について市長の見解を伺いたい。
(1) 新発田市が認識し把握した市職員へのカスタマーハラスメント並びにパワーハラスメントの年間件数と過去5年間の推移について。
(2) パワーハラスメントやカスタマーハラスメント被害を受けた市職員へのメンタルヘルス等サポート状況について。
(3) 市職員へのハラスメントの撲滅に向け、どのような取り組みを庁内で行っているか。また、市職員へのハラスメントに対する市長の考えについて。
(4) 市職員がパワーハラスメントやカスタマーハラスメントを理由にして休職に追い込まれたケースはあるか。