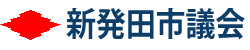
令和6年 9月定例会
令和6年9月12日 (一般質問)
髙橋芳子
録画を再生
1 難聴児の通級指導教室と支援策について
2 吃音の早期発見と早期支援に向けて
1 難聴児の通級指導教室と支援策について
2024年1月に二葉小学校に設置した「難聴通級指導教室」及び「支援策」について伺う。
以前は、難聴通級指導教室に通うには新潟市にある「竹尾四つ葉学園」を利用するしかありませんでしたが、設置が待たれ、このたび二葉小学校に指導教員1名が配置され、5名の児童が通っていると伺っている。
子どもや保護者の不便さに向き合い、さらに成長後の生活や活動に思いをはせる時、市や教育委員会の取り組みはとても大事な施策だと思う。
そこで、以下の点について質問します。
(1) 難聴通級指導教室について
① 現在通っている児童の人数と学年について
② 指導内容と指導時間について
③ 学区外から通う児童の送迎について
④ 検査器具の設置について
⑤ 中学校進学時への個別支援について
⑥ 通級による指導を確実に受けられるようにするための周知や方策について
(2) 補聴器の助成制度の周知と利用状況について
(3) 就学前の難聴児について
① 就学前の早期に難聴を発見することが望まれるが、どの検査や健診で発見できるのか。
② 就学前に発見した場合、保育園やこども園等でどのように対処しているのか。
③ 子ども発達相談室での相談など、目こぼしのない対応ができているのか。
2 吃音の早期発見と早期支援に向けて
吃音は幼児期に発症することが多いとされる。
国立障害者リハビリテーションセンターが3歳児を対象に行った研究では、3歳までに吃音症状を示した、または現在症状があるとした子どもの割合(累積発症率)は8.9%に上った。
新潟県や宮城県など10都県の地方議員の団体は、健診の問診票に吃音と明記した自治体は343のうち1.2%の4市町に留まったと発表した。現状の健診では吃音が十分に発見されない可能性があり、早期発見に向け、問診表の見直しや、保護者にとって相談しやすい環境づくりが望まれるが、当市の現状について伺う。
(1) 各種健診の問診時に吃音の症状がある子どもをどの程度把握できているか。また、症状がある子どもが発見された場合、専門機関の案内をはじめ、保護者への支援・相談等はどのような対応をしているか。
① 3歳児健診時
② 就学時健診時
(2) 子ども発達相談室では、どのような言語・聴覚指導が行われているか。
(3) 言語通級指導教室の参加状況について
(4) 小学校では言語通級指導教室が設置されているが、中学校ではどのような支援・指導をしているか。