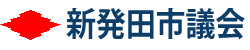
令和6年 9月定例会
令和6年9月12日 (一般質問)
惣山かすみ
録画を再生
1 パブリックコメントの認知度向上と活用について
2 笑顔あふれる対面給食について
3 太陽光パネル等に対する消火活動の安全対策とその周知について
4 新型コロナワクチンの現状の積極的な情報公開について
1 パブリックコメントの認知度向上と活用について
新発田市HPにて、意見公募手続(パブリックコメント)は
市の行政活動の政策形成過程にある情報の積極的な公表を図る
市政への参画の機会を確保する
市民意見を市政に反映する
市民への説明責任を果たす
ことによって、行政運営の公平性の確保と透明性の向上を図るとともに、情報公開と市民参画を基本とした民主的で開かれた市政を推進していくことを目的としています、とあります。
また、インターネットの普及に合わせて、国会でもネットによるパブリックコメントの重要性が話題にあげられました。
そんな中、直近2年間の市のパブリックコメントを見てみると、1件~4件ほどの意見数であり、必ずしも市民が本制度を通して市政に十分に参画しているとは言えない状況であると考えます。
しかし、令和4年度の新発田市過疎地域持続的発展計画案に関する意見公募(パブリックコメント)では、12件の意見がありました。このパブリックコメントは、回覧板にてお知らせがあったようです。このように、お知らせ方法によって意見数の増加、ひいては、市民の市政への参加増が見込めます。市民が市政に気軽に参加できると市への帰属意識が生まれ、定住を促せると考えます。
また、パブリックコメントが少ない理由とされる問題は2つあり、1つはこの制度を市民が知っていないということ、もう一つはそもそも市政への参画に関心がないことです。以上のことから質問致します。
(1) パブリックコメントを実施するお知らせ方法(周知方法)はどのような手段で行っているのか。
(2) パブリックコメントを実施する際の周知方法について
① 回覧板の活用や、若者等が気軽に参加できるよう新発田市公式LINEなどSNSを活用した発信を行ってはどうか。
② 学校配布物としてお知らせすることはできないか。
2 笑顔あふれる対面給食について
新型コロナウイルス禍において、市内小中学校の給食は机を向かい合わせにせず、前方を向いての黙食になりました。昨年5月の感染症5類移行を契機にニュースでは、対面給食に戻し楽しく給食を食べる子どもたちの様子が放送されました。
学校給食の役割は大きく分けて3つの役割があり、1つ目は栄養バランスのとれた豊かな学校給食、2つ目は望ましい食習慣を形成する学校給食、3つ目は人間関係を豊かにする学校給食です。
人間関係を豊かにする学校給食とは、昼の給食の時間は、児童生徒にとって学校生活の中で1日の節目となる時間であり、午前中の学習をはじめさまざまな緊張から解放され、気分転換をはかったり、午後に向けて活力を生み出すことのできる時間でもあります。
また、先日行われた新発田市青少年問題協議会において、コロナ禍における対応の影響が子どもたちに大きな影響を与えていることが話題になりました。学校に行かなくても良い環境があったこと、マスク着用、行事の中止、小学校での縦割り班活動の中止など、様々な理由でコミュニケーション不足となり不登校が増えたことや、大学の4年間を通信授業で過ごし、教師など人間性を重視する職業を敬遠する傾向にあることなどがあげられました。
他にも小さな子どもたちでは、大人の口の動きを見て発音を覚える時期に関わる大人がマスクをしていたことで発語の遅れや間違えた発音で覚えている子が増え、人の表情を読むことや表現するコミュニケーションが薄れてきていると言われています。
そんな中、昨年から徐々に復活している行事や、縦割り班の復活により、子どもたちがコロナ禍前の状態を取り戻すように成長しているのがみてとれます。保護者や、地域の民生委員などからも喜びの声が上がっています。このように、やったらやった分だけ、子どもたちは返してくれます。子供たちの成長にとって、そして社会に役立つ大人になるためには、コミュニケーション力の向上が急務となっています。
そのことから以下、質問致します。
(1) 市内で、対面給食を行っている学校の有無と子ども達と保護者の反応は。
(2) 市内の全ての小中学校の対面給食の再開を検討してはどうか。
3 太陽光パネル等に対する消火活動の安全対策とその周知について
今年3月27日に発生した、鹿児島県伊佐市のメガソーラー火災において、消防隊員4人が負傷、鎮火に20時間以上を要したとあり、リチウムイオン電池を用いた装置が置かれた倉庫が火元で、感電などの危険があり、放水など一切の消火活動ができず、自然鎮火を待つしかなかったというニュースがありました。
また、能登半島地震において、太陽光発電施設や設備が広範囲にわたり多数破損し、石川県穴水町では、斜面に数百平方メートルにわたって敷き詰められていた太陽光パネルが崩落し町道を塞ぎ、同県珠洲市ではスーパーの屋根に設置されていた太陽光パネルが建物ごと倒壊し長期にわたりそのまま残された状態でしたが、スーパーの経営者は発火の恐れや環境汚染があることを知りませんでした。
太陽光パネルは、破損した場合でも、浸水した場合でも、日光が当たれば発電を行う可能性があるため、感電や火災が起きる恐れがあり、消火については通常より距離をおくなどの対応が必要です。また、太陽光パネルには、鉛、セレン、カドミウム等の有害物質が使われている場合があり、土壌や水源に流出した場合は、環境汚染を引き起こすこともあります。
破損した太陽光パネルの取り扱いについては、経産省が令和元年10月31日に太陽電池発電設備による感電事故防止についての注意喚起をしています。そのなかには、自治体でも住民に周知をお願いします、とあります。
経済産業省が2012年7月に開始された「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(FIT法)」に基づく固定価格買取制度や、市においても個人住宅向け太陽光発電設備と蓄電池の導入に関して補助金を設けていることから、今後さらに太陽光パネルの増加が見込まれます。(経産省資源エネルギー庁のHPによると、新発田市の2024年3月末時点における10kW未満の太陽光発電設備導入件842件)
このような状況の中で、災害時における環境汚染や事故発生のリスクについても、過去の事例も踏まえたうえで改めて広報やポスター等により広く市民に周知することが必要と考えますがいかがでしょうか。
4 新型コロナワクチンの現状の積極的な情報公開について
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、令和5年5月8日に新型インフルエンザ等感染症(2類相当)から季節性インフルエンザと同等の5類感染症に変更となり、感染症として危険性が最も低い分類とされました。新型コロナウイルスは変異を繰り返し感染した場合の重症化率は低くなっており、厚労省資料で示された新型コロナウイルス感染症の重症化率は令和4年8月時点で季節性インフルエンザを下回っています。その後も変異を繰り返している新型コロナウイルスについて、ワクチンが実際のウイルスの変異に追いついていない現状があります。
新型コロナワクチンは予防接種健康被害救済制度において、令和6年7月31日現在、申請件数11,645件、認定件数7,835件、認定件数の内、死亡一時金または葬祭料が747件、障害年金 103件、障害児養育年金1件となっている。平成21年から申請受付が始まったインフルエンザワクチンの予防接種健康被害救済制度の申請状況においては令和3年末時点で認定件数191件、 内、死亡一時金または遺族年金等25件、障害年金27件、障害児養育年金0件となっており、新型コロナワクチンにおける健康被害は、わずか3年余りでインフルエンザワクチン15年間の健康被害を大きく上回っています。
10月より市の助成を受けて、65歳以上において新型コロナウイルス感染症の定期接種が始まろうとしています。
市民が感染症対策と予防接種について適切に判断を行うためには、感染症に対する情報と共に、ワクチンの不都合な反応も含めた多面的な情報を積極的に公表することが大切だと考えます。
熊本県熊本市のHPでは、市内予防接種健康被害救済制度の申請数、調査済み件数、認定数、否認数、死亡数、また、総接種回数、副反応疑い報告件数と内容がわかりやすく記載されています。当市においても積極的な情報公開を検討いただきたいと考えますがいかがでしょうか。