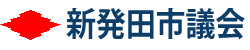
令和6年 9月定例会
令和6年9月12日 (一般質問)
三母高志
録画を再生
1 子ども条例制定について
2 まんが図書コーナー設置による居場所作りについて
1 子ども条例制定について
日本ユニセフ協会のHPにある「子どもの権利条約」の説明によれば、『子どもの権利条約は、子どもは「弱くておとなから守られる存在」という考え方から、それだけではなくて、子どもも「ひとりの人間として人権をもっている」、つまり、「権利の主体」だという考え方に大きく転換させた条約です。子どもを権利の主体ととらえ、おとなと同様にひとりの人間としてもつ様々な権利を認めると同時に、成長の過程にあって保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めているというのが、子どもの権利条約の特徴です。子どもの権利とは、子どもの人権と同じ意味です。子どもは生まれながらに人権をもっていて、それは、義務と引き換えに与えられるものではなく、また、何かをしないと取り上げられるものでもありません。子どもの権利条約においては、子どもが「権利の保有者」であり、それを守る「義務の担い手」は、国です。国は、法律や政策などを通じて、条約に定められた子どもの権利の実現につとめます。また、条約には、子どもを育てる責任はまず親にあり、国がそれを支援するということも書かれています。』と記載されている。
さて、私は昨年9月の定例会で新発田市の「子ども条例制定」について質問を行い、市長ならびに教育長から答弁を頂いた。市長答弁では国の「こども大綱制定」や「新潟県の子ども条例制定」を参考に新発田市の条例制定に取り組むとの答弁を頂いている。
また、条例制定にむけ新発田市こども課では市内の子どもを対象としたアンケートの実施やワークショップの開催など、子どもたちの意見を反映させるための取組が行われている。
ついては新発田市の子ども条例制定にむけて、重要と考える何点かについて伺いたい。
(1) 「子どもの権利条約」には、子どもたちが持つ基本的な4つの権利である「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」と、政府や親、地域社会や民間セクターが子どもに関連する行動を取る場合の基本となる「子どもの最善の利益」「差別の禁止」「子どもの参加」「生存と発達」の4つの原則が掲げられ、日本の「こども基本法」にも取り入れられている。
新発田市で制定される「子ども条例」にはこうした権利や、原則について記述され、広く新発田市民に周知されるべきと考えるが如何か。
(2) 条例制定にあたり条例の目的や効果を考慮し、新潟市が令和6年4月に改正し施行した「新潟市子ども条例」の「第4章 権利の侵害の救済」を新発田市の条例にも盛り込むべきと考えるが如何か。
(3) 「権利の主体」として、条例制定時から子どもが参加し関わり、その後の具体的な施策の展開や運営等にも子どもの参加が求められるが、どのように取り組むのか。
① 全体的な取り組みについて
② 教育的な観点に基づく取り組みについて
(4) 国際NGO公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが2022年3月に実施した「学校生活と子どもの権利に関する教員向けアンケート調査」では子どもの権利について「内容までよく知っている」教員は約5人に1人(21.6%)で「全く知らない」、「名前だけ知っている」教員は、あわせて3割にのぼる(30.0%)が、新発田市の教員の認識状況について伺う。
(5) 条例制定や施策展開にあたり、子ども達の様々な問題の解決に向かうためには、教育委員会との緊密な連携が必要と考えるが、その具体的な方法と課題について伺う。
2 まんが図書コーナー設置による居場所作りについて
漫画は日本の文化であり、子どもや大人にとって大切な娯楽である。コロナ感染症による巣ごもり需要や電子書籍の普及により2020年の日本のコミック市場の推定販売金額は6126億円となり25年ぶりに最高額を更新した。また昨年2023年の販売金額は6937億円で電子書籍が大きく伸び、根強いファンや読者がその文化を支えている。
新発田市では中央図書館をはじめ、歴史図書館、市内各地の公民館やコミュニティセンターに設置された分館や分室に配備された図書利用が可能となっている。
しかし蔵書としての漫画本は一部の作品に限られているようだ。
例えば、歴代最大の発行部数5億1000万部を誇る「ONE PIECE(ワンピース)」尾田栄一郎作は見当たらない。
ついては以下について伺いたい。
(1) 新発田市が管理する図書館では漫画本は何作何部所有しているのか。また購入等の基準はどのようになっているのか。
(2) 市民に不要となった漫画本等の寄付を募り、図書館や市内のコミュニティセンター、公民館、ユウネスしばた児童運動センターなどに、まんが図書コーナーを設置し、居場所作りに活用できないか。