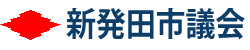
令和6年 6月定例会
令和6年6月6日 (一般質問)
長島徹
録画を再生
1 新発田市の小・中学校の「いじめ・不登校」について
2 新発田台輪の今後さらなる300年に向けて
1 新発田市の小・中学校の「いじめ・不登校」について
令和4年度、全国の小・中学校で不登校児童生徒数が約30万人、全国小・中学校、特別支援学校でのいじめの認知件数が68万件超と、何れも前年を大きく上回っています。同じく令和4年度、新潟県では小・中学校での不登校児童生徒数が、前年度より905人増の4,759人、いじめの認知数は、前年度より1,610件減の19,644件でした。これを踏まえ、当市の現状について伺います。
(1) 令和5年度、小・中学校の不登校児童生徒の人数と不登校に認定されなくても、学校を休みがちな児童生徒の人数について
(2) 児童生徒が、不登校や学校を休みがちになった理由について
(3) 教育支援センター車野校について
① 現在登録している児童生徒の人数は
② 市内小・中学校に通う全ての児童生徒が、学校に行くのが辛くなった時に登録や手続き無しで、自由に半日や一日だけでも駆け込み寺的に利用できるようにしてはと考えるが如何か
(4) 登校はできても教室に入れない児童生徒の受け皿となる校内教育支援センター設置の状況や、「学びの多様化学校(不登校特例校)」についての新発田市としての考えについて
(5) スクールソーシャルワーカーとスクールサポートスタッフの現状の人数、それぞれの役割、また連携がどのようになっているかについて
(6) 令和5年度、小・中学校におけるいじめの認知数について
(7) いじめと認知した時、いじめられた側・いじめた側にそれぞれどの様な対応をされているかについて
(8) 教職員などから、児童生徒に対して「体罰・暴力的言動・ハラスメント」等に該当する行為の有無について
(9) 新潟県教育委員会から、毎年行われている教職員等から生徒に対しての体罰等の調査について、実施時期と何か問題などがあった場合の市側の対応について
(10) 教育現場での「いじめ」は、何故無くならないのかについて
2 新発田台輪の今後さらなる300年に向けて
新発田市各地に在る様々な地域の心・誇りである伝統文化・まつりが、今も各地で守られて、受け継がれてきています。しかしながら、少子高齢化に伴う人口減少等により、それらの存続が困難になったり完全にできなくなっている所もあるのではないかと推察します。
私も、半世紀近く携わっている「新発田台輪」にも当然同じことが言えます。新発田台輪の歴史は、1726年6代藩主溝口直治候の命により始まったとされています。もう間もなく300年の節目の年を迎えます。
現在、各台輪を取り巻く環境は、様々な面で厳しさを増しています。先に述べましたが、少子高齢化に伴う人口減少そして、中心部の空洞化等があり、台輪の維持管理・保存に掛かる膨大な費用と人の問題や、「好きだからやっている!」では、立ち行かなくなっている面も出てきています。「台輪」を所有する各町内は、先人から受け継いできた「新発田台輪」の「伝統・祭事の所作」を時代が変化しても変えることなく、次の世代、更なる300年もつないでいくため、「維持管理・保存」の取組みをしっかりとしていかなければなりません。
上記を踏まえ伺います。
(1) 新発田市にとって「台輪」とは何か。また、市長の「台輪」に寄せる思い考えについて
(2) 「台輪保存」を基軸とした、次の300年を目指し、未来への投資として更なる支援の考えについて
(3) 民俗文化財の台輪保存修理の範囲は現在、台輪本体と台輪周りの提灯が対象であるが、保存修理の範囲を拡大する考えについて
(4) 新発田市が所有管理・保存する3台の新発田っ子台輪の利活用をどのように考えているかについて
① 観光面について
② 教育面について